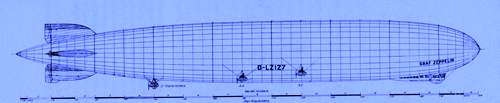
「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航

第二、第三区間
帝国劇場 - タイプライター - 出発
祝宴、パーティ、記念撮影、千人規模の晩餐。日本政府はそれに招待した。
知識人、軍人、商社員、通訳などがいた。だが、教養のある日本人の多くはドイツ語と英語を流暢に話すことができた。
両国に関する演説が行われた。窓から新聞記者のためだけに行われるような演説でもなかった。
ここでは飛行船を象徴とする両国民の共同作業への明確な意志の声が高まっていた。
十万もの論説、何千もの演説、何千もの実際的な関係をもってしても、ドイツの名に再び栄光と権威をもたらすには苦労と時間が掛かったが、ツェッペリンは数分のうちに、霧も障害もことごとく突き破り、それを成し遂げた。
ドイツの外交政策は、民衆の深層心理にかかわるこうした事実を取り逃がしてはならない。それは、熱いうちにしか鍛えることのできない鉄のようなものだ。公的な「かまど」だけで事足りると思ってはならないのだ。
夕刻、ドイツの市立劇場に相当する帝国劇場に出掛けた。
ある日本の芝居が上演されていた。
勇者が刀で互いに斬り合い、赤く化粧を施した頭が舞台上の戦場に落ち、長い対話が続いており、日本人の男女はそれを見て笑い転げていたが、我々はそのあいだ、座ってそれを陰惨な悲劇だと思って見ていた。
さらに、我々は笑ってこれ以上汗をかくのを気にしていた。
劇場全体、平土間、桟敷は揺れる扇子の唯一の森であった。
子供達は劇場のなかを走り回り、小さな子供たちは桟敷席や回廊の至るところで、親の背中で泣き叫んでいた。役者は軽業師のように互いに踊るように跳びはねていた。白く化粧した彼らの顔は、殆ど無表情で動きがなかった。その衣装の色の組み合わせは舞台装置と見事に調和していた。
黒装束の小柄な会場係の女性が、私の肩をつついて合図した。私は彼女について行った。
すでに芸者たちの傍にいるときに一緒に歓談した魅力的な日本人老教授が外に立っていた。その灰色の薄いフロックコートは電気扇風機から吹き付けてくる隙間風に翻っていた。
彼は手に冷えたビールの大瓶とグラスを持っていた。
ああ、日本についてはまだたくさん語ることがある。
だが、いくつかのことは語らないままにしておきたい、私自身のために。
折に触れて、おそらく半年くらい経ったら、それらのことを話すことになるのだろう。
だが、私のタイプライターのことは、述べておかなくてはならない。
私は霞ヶ浦の格納庫の前で、ツェッペリンに乗船するための階段の傍にある砂袋の上に座っていた。私の前には、私の鍵盤付き竪琴の木箱があった。
私は出発が遅延すると電報を出した。最初は2人の水兵がそこに立って見ていたが、それが4人になり、6人になり、とうとう12人になった。
密に並んで立つ水兵たちは、その切れ長の視線を梃子にまで落とした。ほかのもの達は、キーを打つのを見逃すまいと仲間の上によじ登った。
タイプライターが、技術による魔法の機械だと思っている国が未だにあるのである。彼ら独自の文字を打つために、日本人には6千ものキーと少なくとも百本の指が必要であろう。
日本では、英語を書ける者だけがこの小さな魔法の道具を使うことができる。
通常かわいい秘書で慣れているように、この機械は我々のように記述する側の人間にとってはやっかいなものであるが、電信員にとっては読みやすく、また快適になる。
小さな事故のために離陸が遅れたが、ツェッペリン自体の問題ではなかった。被害は迅速に修復された。しかし、風向きがよくなかったので離陸は翌日まで延期された。
8月23日15時、いつもの号令が響き渡った。
「索を放せ!」
2万人の日本人がいた。何百人ものドイツ人が、見えなくなって行くツェッペリンを切ない気持ちで見つめ、別れの挨拶を叫んだ。
日本中のすべての町や村から、人々が離陸を見に来た。
その日は夜通し、そして翌日も半日、格納庫には物見高い人々が群がった。
このときの写真は言葉よりも多くのことを物語っている。日本におけるツェッペリンの思い出は消え去ることはないであろう。
この出来事は、やがて民衆の芸術を支配することになるだろう。教科書に載り、日本の若者の記憶のなかで生き続けるであろう。離陸の際、もはや日本国土の多くは見ることができなかった。
我々の頭の中は、鮮やかな、珍しい光景でいっぱいになり、それらを記憶したスピードがあまりに急激だったので、ツェッペリンが果てしない海上を、その見事な世界周航の後半に旅立ったとき、我々はまるで酔ったようにふらついていた。
我々に唯一つだけ判っていたのは次のことである。
ツェッペリンが毎週、フリードリッヒスハーフェンあるいはベルリンから東京に飛ぶことになるのに、そう長くは掛からないし、掛かってはいけないということである。
少なくとも日本人は、そのための一部に貢献するであろう。